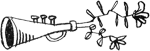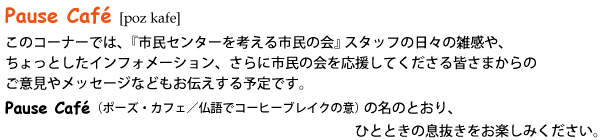
2016.02.25
聞いていて嬉しくなった。私も是非、その方とお話ししてみたい。
――人とつながる街、狛江。本当だ。ViVa 狛江!
2015.11.29
きょうの空
けさ、自宅から公民館に出かけるときに空を見上げるとこんな雲が!
まるで焼き魚を食べた後の骨みたい。楽しくなってしまいました。
(こまねこ)
(こまねこ)

2015.11.25
2015.11.20
2015.11.14
女性であることを生きていて、苦しくて息ができなくなる作品。
それでも心に蓋をせず、自分自身と向き合い、どう生きていくかを選びとっていった・・・そんな彼女を無性に愛おしいと思いました。
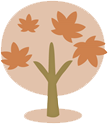 温かいコーヒーを手に、ロビーから眺める森も時間が止まったよう。ニキに癒された一日でした。
温かいコーヒーを手に、ロビーから眺める森も時間が止まったよう。ニキに癒された一日でした。(S.H)
休館日は火曜日なので、月曜日がオススメ。
展覧会ホームページは、こちら。
2015.09.29
(みのだ)
2015.09.26
(米岡裕美/埼玉医科大学 医学部教養教育 講師)
2015.09.23
9月19日、中央公民館で開かれた 中間報告会 は100名近くの人が会場に詰めかけました。圧巻だったのは、20代から30代の若手グループ(東大で都市工学を学ぶ大学院生等)によるプレゼンで、会場が大きく沸きました。
(ジャスミン)
2015.09.09
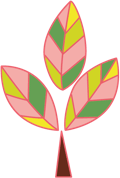 と、普通その長には男性が座りますが、ここは、ちがう。 この会に参加して、狛江市がどのようなまちか、よくわかるようになりました。
と、普通その長には男性が座りますが、ここは、ちがう。 この会に参加して、狛江市がどのようなまちか、よくわかるようになりました。(YK)
2015.06.20
●本好きの方へ6月13日の図書館分科会で、大澤正雄先生のお話を聞きながら、レイ・ブラッドベリーのSF小説「華氏451」を思い出していました。
管理主義の国家によって、文字を読むことはもちろん、書物を持つことすら禁じられている世界の物語です。主人公は「ファイアーマン」。隠された書物を探し出し、火炎放射器で焼却するのが任務です。題名の華氏451とは、紙の燃え上がる温度のこと。
書物は人の心を乱し、平和な社会に害毒をまき散らすものであるから、徹底的に処分。禁を犯した者は厳罰に処されます。国民は双方向テレビと時間を共にし、考えることを放棄しています。そうした社会に抵抗する「ブックピープル」と呼ばれる地下組織の人々の話は、書物を熱愛したレイ・ブラッドベリーならでは。60年以上も前に書かれた小説ですが、古さは感じられません。F・トリフォー監督で映画にもなっていてDVD化もされています。こちらもおすすめです。
(こまねこ)
2015.06.14
(1)「公民館運営審議会」って?狛江市には、公民館運営審議会という、公民館長の諮問に応じ、公民館の各種事業(講演会、講座など)について調査審議を行い、公民館活動の振興を図る役割を担っている審議会があります。今年の4月に改選が行われ、新しいメンバーでのスタートとなりました。
前期から学識経験者として関わってくださっている伊東静一先生を講師に、5月12日(火)19時委員学習会が開かれました。
市民センターを考える市民の会のメンバーが学習会を傍聴しましたので、感想を紹介します。
一番初めに「公民館とは地の智を知り、地の智をつなぐところ」と言われたのが心に残りました。また、公民館には職員の役割が重要であることも改めて感じました。市民センターを考える市民の会の分科会につながる内容でした。(M.S)
「公民館」は、住民から市民への一つの大きな道である。施設(ハード&ソフト)の継続が更に難しいことになっていると感じました。
簡単に言えば、低コストの場所だけを求めることに対応したり、安価でメリットの大きいことを求める人々が多いということ。
狛江で本物の公民館の発展をと思いました。(T.F)
(2)TBSテレビ 噂の!東京マガジン「市民の生きがいどこへ〜公民館閉鎖で混乱」 2015.6.14放送
習志野市公共施設再編方針の計画の中で、公民館の統廃合を取材した番組でした。
こまえ市民センターの改修に関して、狛江市が市民に対して情報を開示せずに強引に進めた、その中で行政が使っていた表現と全く同じ言葉で習志野市公民館の統廃合の正当性が説明されていることに驚きました。(笑)
行政の優先順位は「経費削減」
市民は「地域コミュニティーの重要性」「市民が誇れる文化のまち」
どちらも大切にできるまちづくりは不可能なのでしょうか。
今私たちが取り組んでいることは、まさに時代の流れの中の大事な試みなのかもしれません。(S.H)
2015.05.26
オススメドキュメンタリー映画 「みんなのアムステルダム国立美術館へ」
アムステルダムの美術館改修に10年もかかってしまった 。その舞台裏がとても面白い映画になったので観に行って来ました。
狛江と同じことがオランダのアムステルダムでも起こってる?!
みんなが良かれと思って取り組む中で美術館の改修に10年もかかってしまう…。民主的であることは、まったくもって大変なのですね。
立場の違う人の、それぞれの思いが強いからこそのぶつかり合い。
みんな本当に真剣で、関わった多くの人々の「美術館を良いものにしたい」という思いの強さが羨ましかったです。(SH)